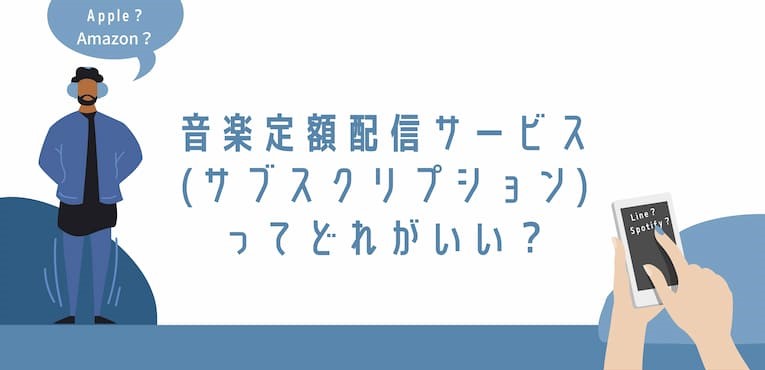優里メジャー2作目の楽曲となる「ドライフラワー」
数々の国内チャートで首位を獲得しました。
メジャー1作目となった「かくれんぼ」のアフターストーリーとなっており、SNSでも数え切れないほどの拡散、言及、カバーがされています。
全体を通して
弾き語り映えのするシンプルなローコード中心の楽曲で、よりメロディーや歌詞にウェイトを置いた作り方がされているように感じます。
全体的に『C→G→D→Em』の土台のコードがあり、ワンコーラスで見てもBメロ以外はこの進行が若干変化した形という点で同じです。
テンションを乗っけたり、コード進行に強制力の強い動きを生み出すためのセカンダリードミナントが使われています。
Aメロ
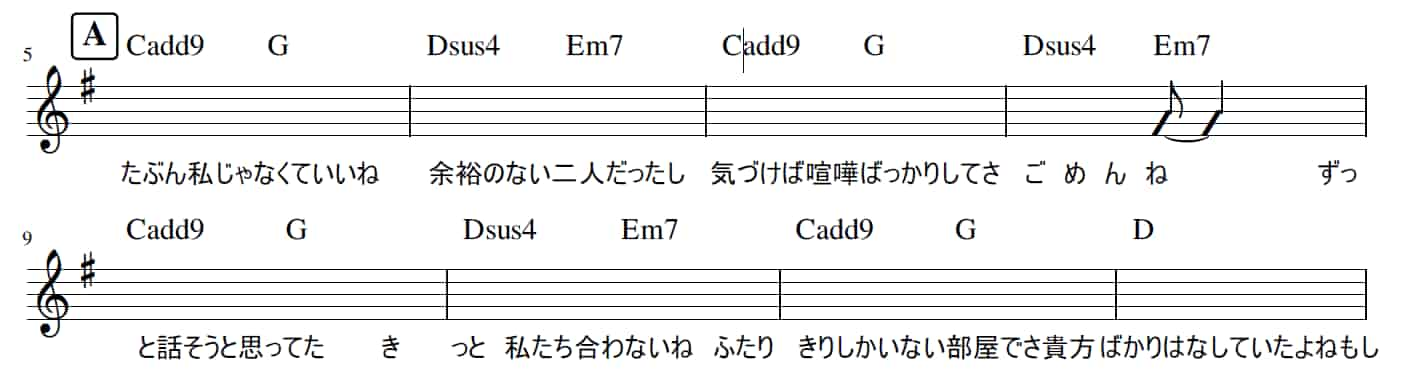
キーGで見ると、Aメロで使われているコードはすべてダイアトニックコードで構成されています。
特徴的な点としては、『C』が『Cadd9』、『D』が『Dsus4』になっている部分でしょうか。
1~2小節(Cadd9→G→Dsus4→Em7)
ここは、トップ2つの音を固定するためのコードアレンジと考えることができそうです。
ギターで弾いてみるとわかりやすいのですが、『レ(D)』『ソ(G)』の音が常に固定された進行になっています。
| コード | 構成音 |
|---|---|
| Cadd9 | C,E,G,D |
| G | G,B,D |
| Dsus4 | D,G,A |
| Em7 | E,G,B,D |
上の表のように2小節間の4つのコードに『D』『G』が入っており、そのコードを循環していく形になります。
コードチェンジが非常に簡単なうえ、哀愁のある響きで好んで扱う方が多いのです。有名どころで言えば、「ソラニン/ASIAN KUNG-FU GENERATION」でしょうか。
もちろんキーは違うのですが、『Ⅳadd9→Ⅰ』という同じ動きをしています。
8小節目(D)
ここまでDsus4バカリ使われていましたが、8小節目は『D』が使われています。
Bメロ
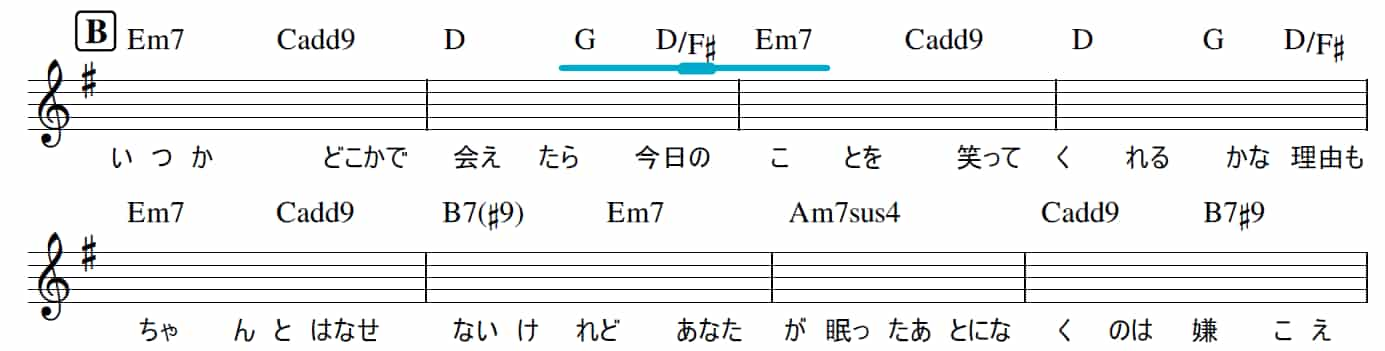
2小節目(D/F#)
このコードは『G→Em7』の動きを滑らかにする役割があります。
上のコードは緊張感のあるドミナントコード(D)であり、ベース音がF#であるため、安定感の強いEmコードへと自然な流れで進んでいきます。
5小節目(B7(#9))
Bメロ5小節目、8小節目、またサビに多く現れる『B7(#9)』のコードは、Em7へのセカンダリードミナントコードです。
セカンダリードミナントは、あるコードをトニックと見立てて、5度上のコードをそこへのドミナントモーションをとるドミナントコードに変えることができます。
これによりBm7がB7へと変化しているのです。
7小節目(Am7sus4)
AメロではDとGの2音が固定されていると解説しましたが、なかでも一曲を通して強く固定されているのがD音です。
先程のB7(#9)でもそうでしたが、今回はAm7sus4の『sus4』の音がD(レ)に該当します。
この曲はDの音を常に意識してコードをアレンジしているのでしょう。
サビ
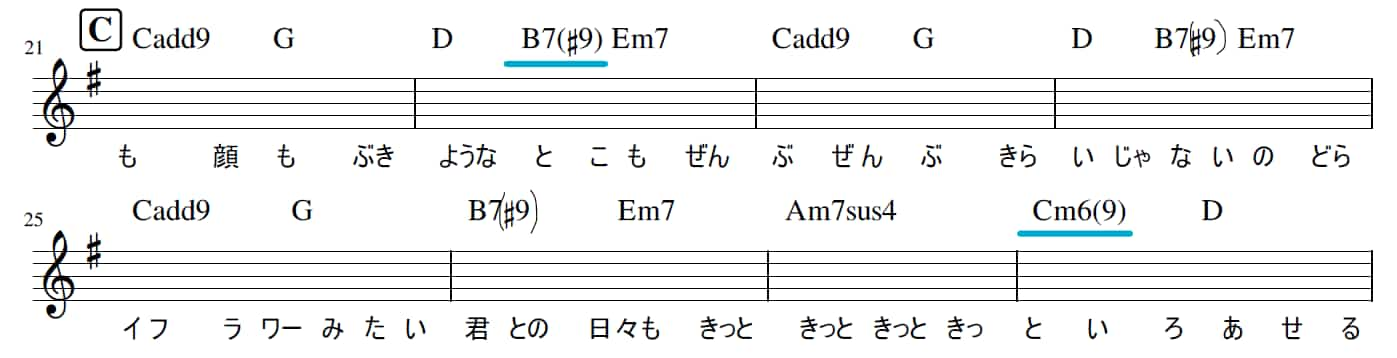
サビでもB7(#9)が出てきますね。
Bメロでも解説したので、ここでは割愛します。
8小節目(Cm6(9))
CmはキーGからみたサブドミナントマイナーコードとして解釈できます。
サブドミナントマイナーは、そのキーの同主短調(Gマイナーキー)のⅣmコードを借用してきたものです。
サブドミナントマイナー(Ⅳm)のよく使われる形は以下の3パターン。
- Ⅳm
- Ⅳm7
- Ⅳm6
Cm6(9)の『9』は、ずっと意識して固定されていた後D音です。
今回は、藤井風さんの『きらり』を分析していきます。 『ホンダ ヴェゼル』のCMソングに起用された楽曲です。 曲の爽快感と楽しくも涼し気な映像が最高にマッチしていて、青春のようなきらめきが感じられました。 ここからの内容は、er-m[…]
まとめ:歌詞も解釈してみよう
一曲を通してD(レ)の音が常に意識されている楽曲でした。
こうした固定する音をペダルポイントと言いますが、ペダルポイントからコードのアレンジをしていくのも作曲手法の一つです。
そのせいか、楽曲にまとまりや落ち着きが強く感じられて、コードワークに煩わしさがなくボーカルが際立つように感じました。
今回は、コード進行や演奏の観点で分析を行ってきましたが、この楽曲の魅力は歌詞にもあります。
『なるさんの考察日記』様では、ドライフラワーの切なさの正体を歌詞の観点で解釈されています。
是非ご覧ください。