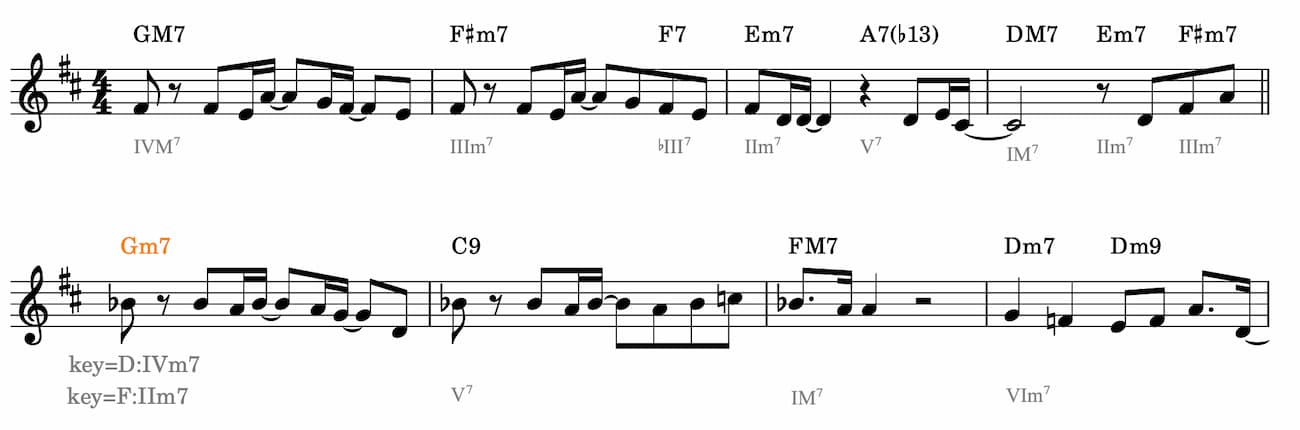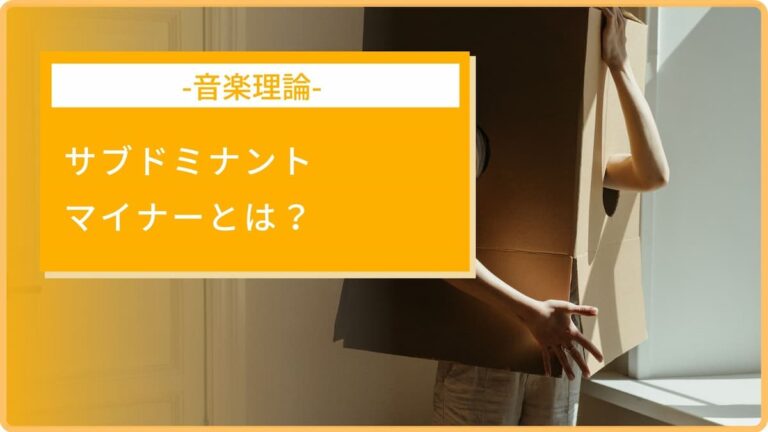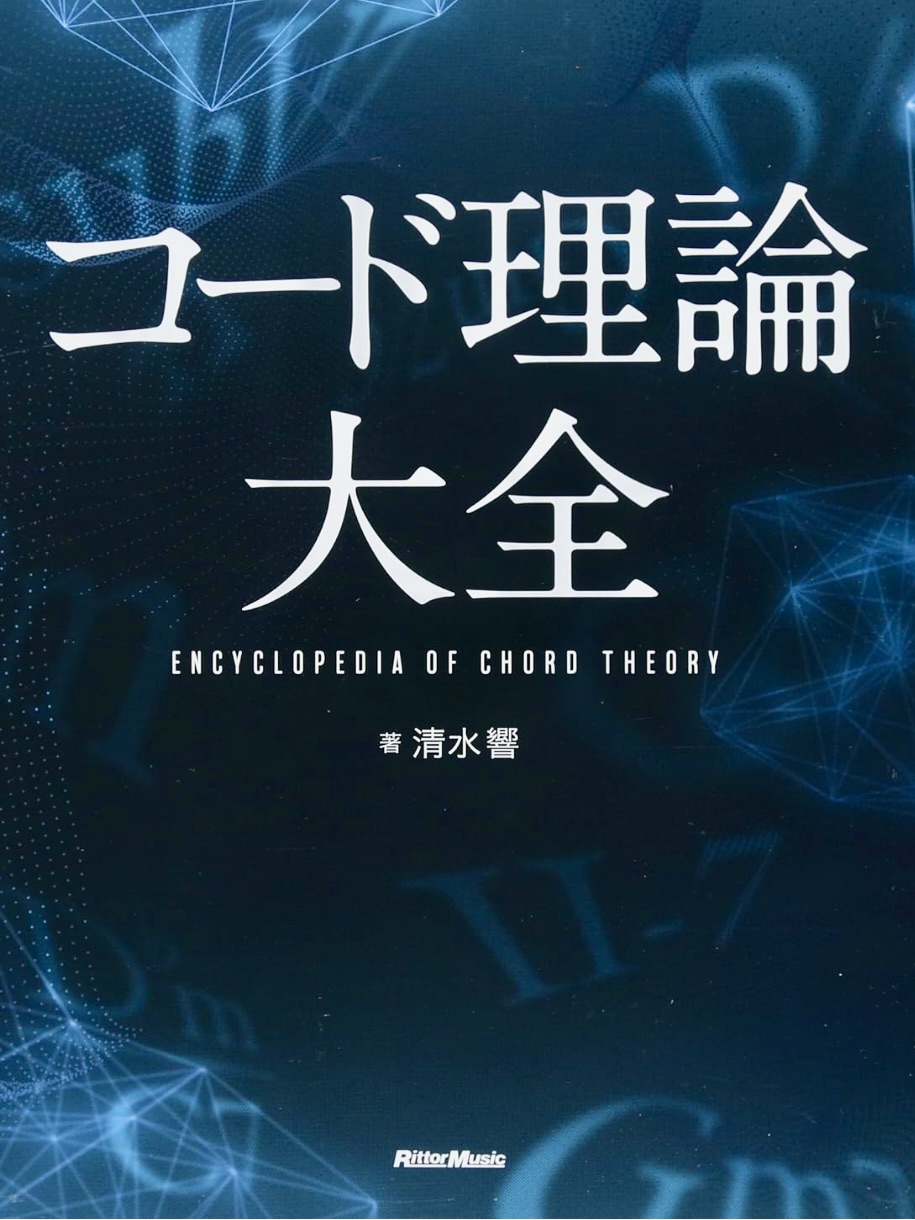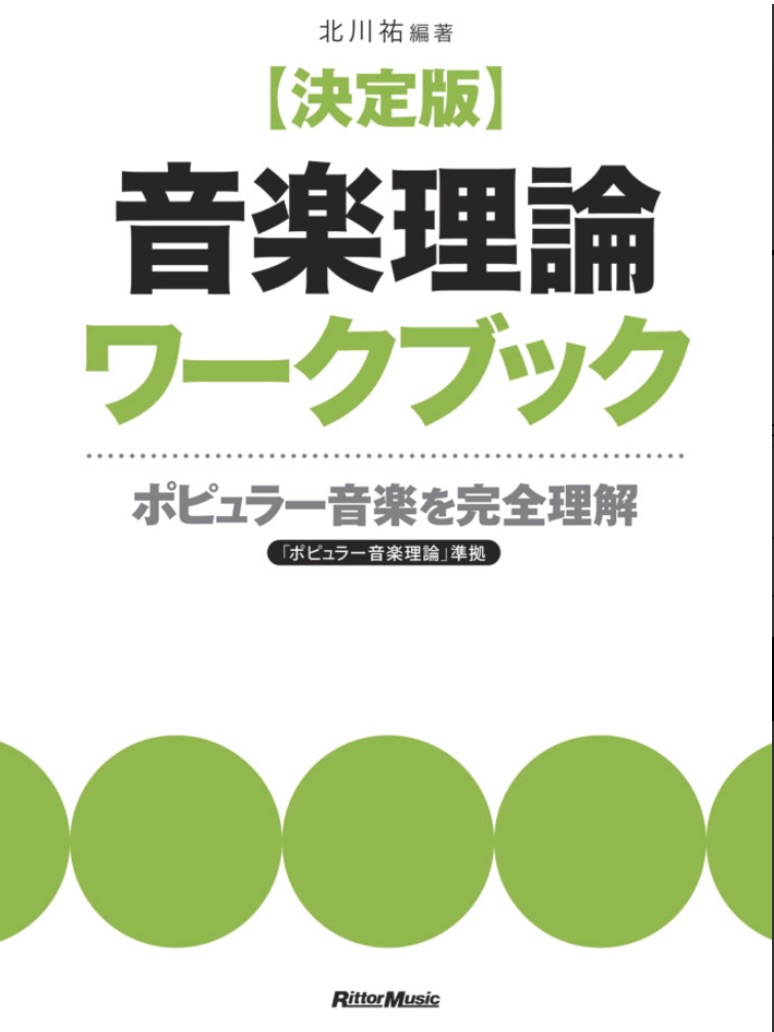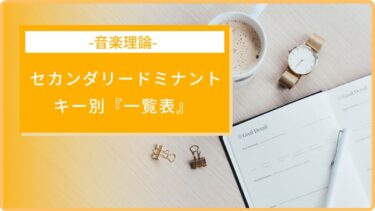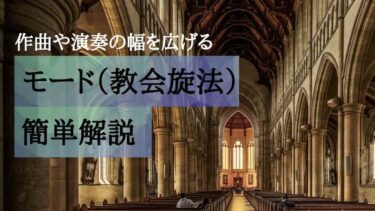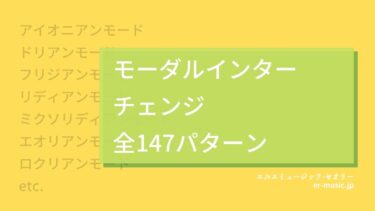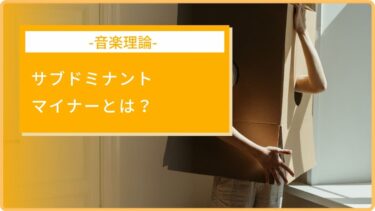ノンダイアトニックコードのうち、JPOPでも頻繁に使われるものにサブドミナントマイナーコードがあります。
単純に、マイナーキーでサブドミナントに当たるコードをサブドミナントマイナーと呼んだりもしますが、
この記事では、ノンダイアトニックコードとしてのサブドミナントマイナーを解説していきます。
ノンダイアトニックコードについてはここちらをご覧ください。
サブドミナントマイナーとは
サブドミナントマイナーとは、メジャーキーの中でサブドミナント(IV)をマイナーコード(IVm)にした、ノンダイアトニックコードです。
哀愁ある響きで、叙情的な雰囲気を出したい際によく使われます。
例えば、Cメジャーキーの場合はFがサブドミナントですので、Fm(Fm7やFm6も含む)がサブドミナントマイナーに当たります。
実際に音を聞いてみましょう。

このIVmは、同主短調のサブドミナントです。
サブドミナントマイナーは、一時的に同主短調からコードを借りてきたものと言えます。
同主短調などからコードを借りてくることをモーダルインターチェンジと言います。
サブドミナントマイナーの特徴
サブドミナントマイナーは、サブドミナントよりもドミナントの雰囲気を持っています。
サブドミナント(IV)がマイナーコードになるということは、3度が半音下がります。
Cメジャーキーで例を見てみましょう。
| コード | 構成音 |
|---|---|
| C(トニック) | C,E,G |
| F(サブドミナント) | F,A,C |
| Fm(サブドミナントマイナー) | F,A♭,C |
FがFmになると、構成音AはA♭になります。
トニックの構成音に隣接する音が2つ(FとA♭)となり、ドミナントほどではないですがトニックへの接続がスムーズになります。
そのため、サブドミナントに比べてドミナント要素の雰囲気を持ちます。
サブドミナントマイナーと言えるコード
FがFmになる例から、サブドミナントマイナーコードと言える条件は以下2つと言えます。
- サブドミナントの機能を持っているコードこと
- トニックからみた♭6の音(キーCでいう『ラ♭』)を持っていること
この条件で考えると、以下のコードをサブドミナントマイナーと分類できます。
- Ⅳm,Ⅳm7,ⅣmM7,Ⅳm6
- Ⅱm-5,Ⅱm7-5
- ♭ⅡM7
- ♭Ⅵ,♭ⅥM7,♭Ⅵ7
- ♭Ⅶ7
D♭M7は、サブドミナントDm7のサブドミナントマイナー化Dm7-5から、さらにルートを半音下げた形です。
トニックへと半音下降できる進行となるので、裏コードに近い印象があります。
A♭7はサブドミナントマイナーである、A♭M7をもっとブルージーセブンスコードに変えたものです。
B♭7はDm6に近しい構成音でありますし、A♭の音も含んでいます。
サブドミナントマイナーの使い方
サブドミナントマイナーがどういったコードなのか理解したところで、どの様に使うのかを確認していきましょう。
アイデア次第で相当数の使い方が考えられますが、ここでは以下の様なよく使われるサブドミナントマイナーの使い方を紹介します。
- IVをそのままIVmに置き換える
- IVを『IV→IVm』に分割する
IVをそのままIVmに置き換える
最も簡単な使い方は、『IV』をそのままサブドミナントマイナーである『IVm』に置き換える方法で、基本的にいつでも使えます。
ただ、メロディーとの兼ね合いは考える必要があり、メロディーとぶつかってきもち悪いと感じる場面では回避しましょう。
例としてCメジャーキーで考えますが、F(IV)がFm(IVm)になると構成音に『A♭』の音が入ります。
Fmのこの時メロディーで『A』がなる場合は、構成音にAが入るF(IVm)を使用した方が安全です。
とはいえ、Fmの上で『A』がなることがNGな訳ではありません。
構成音『A♭』とメロディー『A』が1オクターブ以上離れていれば、いくらか違和感を解消できますし、サブドミナントマイナーの良さを取り入れることができます。
IVを『IV→IVm』に分割する
コード進行の中で『IV』が登場する際に、『IV→IVm』という進行に置き換える方法もよく使われます。
前項の、「IVをIVmに置き換える方法」よりは、使用される場面が限られている印象です。
これは、『IV→IVm』の動きで、3度の音が下行する動きができているためです。
ノンダイアトニックコードの緊張感がありながらも、少し落ち込んでしまった様な暗く落ち着いた雰囲気となるため、その後のコードとの相性の良し悪しが感じやすいのです。
以下では、『IV→IVm』がよく使われるシーン2つを解説します。
- IV→Iの進行を、IV→IVm→I
- IV→IIImの進行を、IV→IVm→IIImへ
いずれもCメジャーキーで紹介します。
IV→Iの進行を、IV→IVm→I
サブドミナントからトニックへ進行する進行は、4小節や8小節単位で訪れるような区切りとなる箇所では変終止やアーメン終止と呼ばれたりします。
このIVがIに解決する進行を、『IV→IVm→I』にしてみます。
IV→I
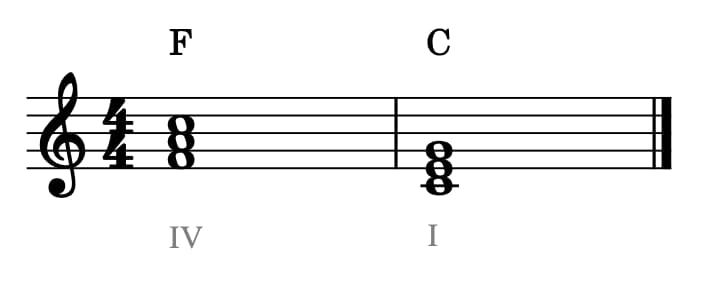
IV→IVm→I
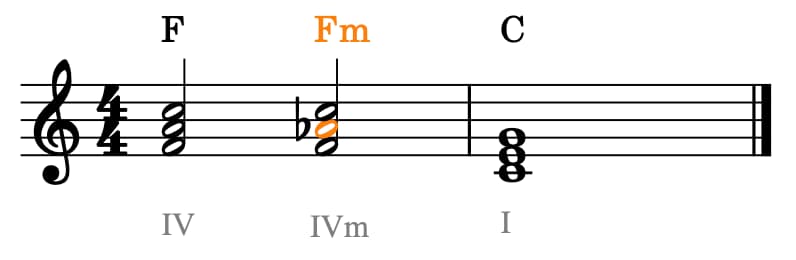
IV→IIImの進行を、V→IVm→IIImへ
先ほどはトニックのIへ解決しましたが、次はIIImへ下っていく進行です。
IV→IVmの変化で下行感が出ているため、IIImへの進行は、感情の起伏が少ない穏やかな展開に感じられます。
(下の例では、IIIm終わりで心許ないのでVImまで進行させています。)
IV→IIIm→VIm
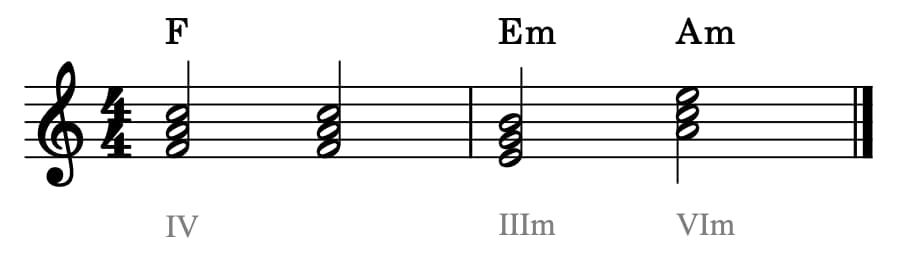
IV→IVm→IIIm→VIm
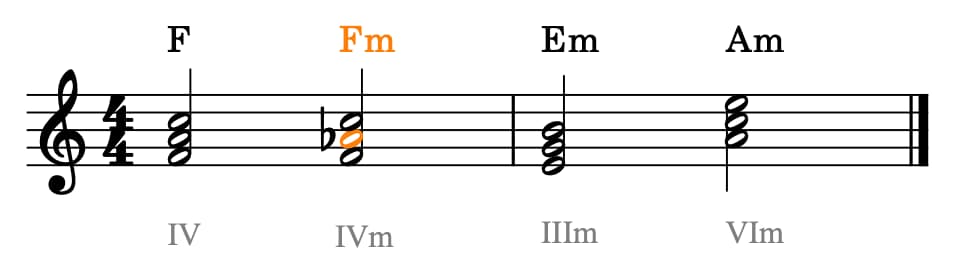
サブドミナントマイナーの有名曲での使用例
ここからは、サブドミナントマイナーのさまざまな使い方を、実際の楽曲を交えて紹介いたします。
サブドミナントマイナーのイメージを明確にしていきましょう。
- IVm→V(ドライフラワー/優里)
- IV→IVm(LADY/Official髭男dism)
- IVm→転調(きらり/藤井風)
IVm→V(ドライフラワー/優里)
『IV→V』の一般的な進行を、『IVm→V』に置き換えたコード進行です。
ドライフラワーでは、サビの最後でサブドミナントマイナーを使用しています。
力なく盛り下がっていくようで、やるせない雰囲気を感じます。
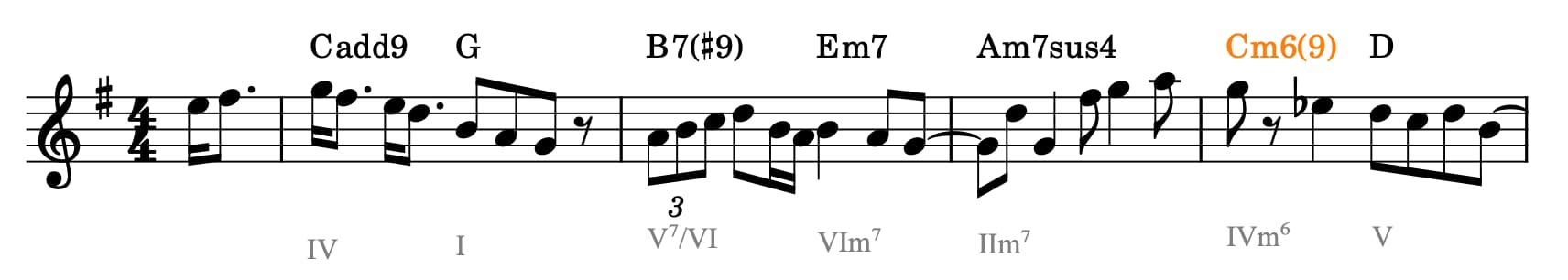
IV→IVm(LADY/Official髭男dism)
『IV』単発の進行を、『IV→IVm』に分けたコード進行です。
サブドミナントマイナーの哀愁や、進行感も強まり、クライマックスとしても使いやすいコード進行になっています。
LADYでは、サビ前半の『DM7』を、後半で『D→Dm』に変えています。
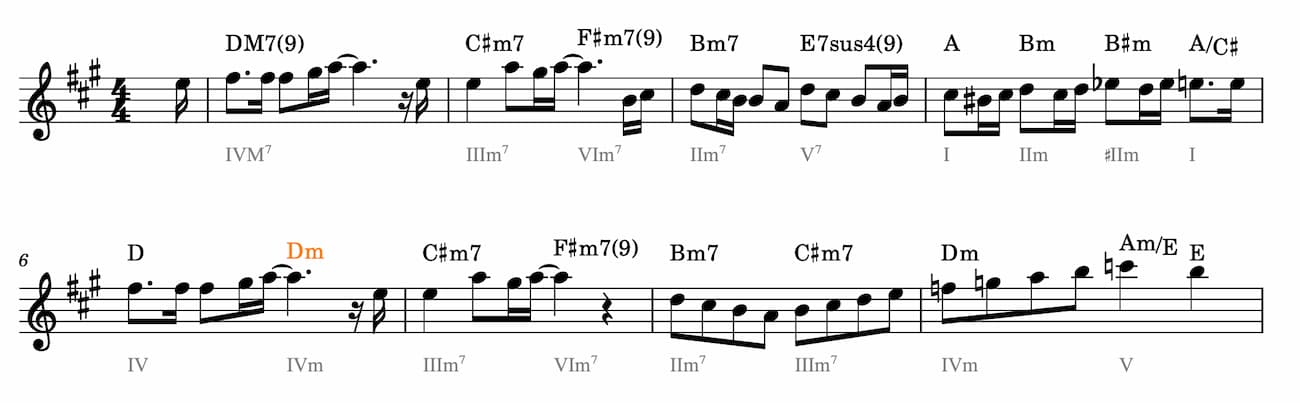
IVm→転調(きらり/藤井風)
『IVm』が転調のきっかけとし利用される場合もあります。
IVmは、同主短調のIVmでもあるため、同主短調への転調がスムーズにできます。
特に、藤井風の楽曲でよく使われています。
『きらり』では、キーDのIVmを、キーF(Dm)のIIm(IVm)と考えて転調をしています。