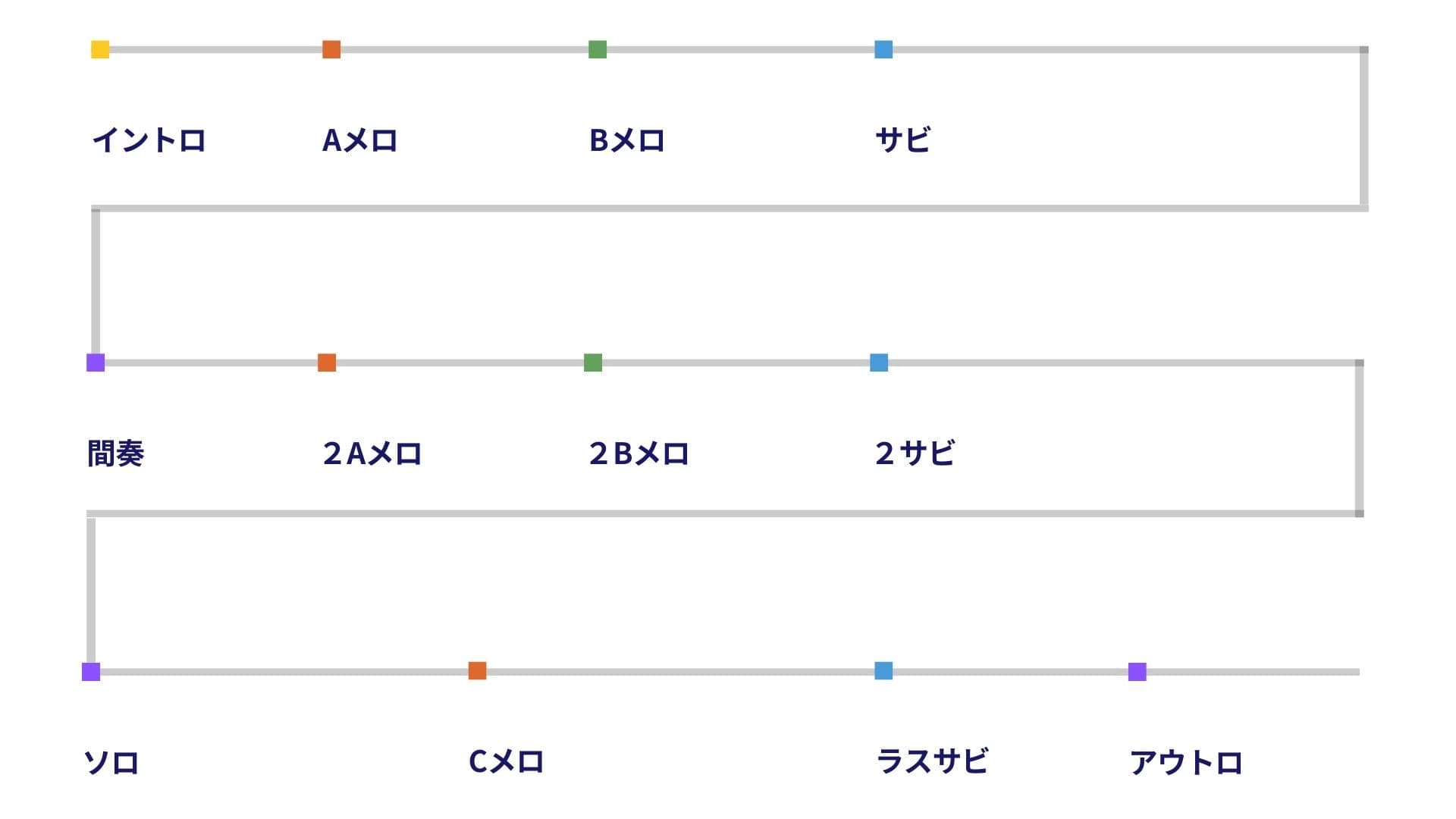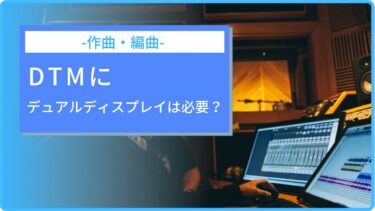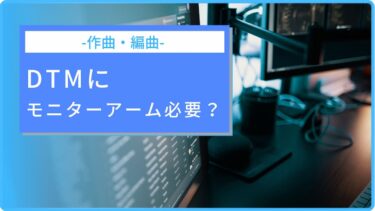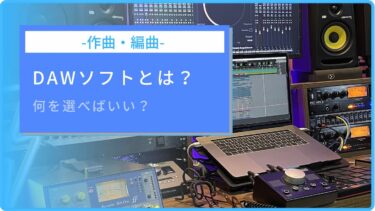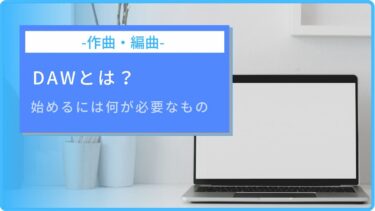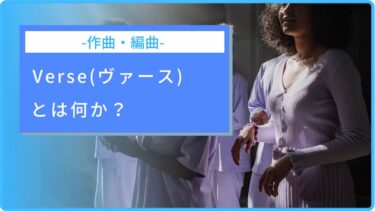Aメロを簡単に説明すれば、最初にボーカルの歌が入るパートのことです。
メロディーや演奏が変化し「なんだか雰囲気が変わったな」と感じたら、そこからはBメロです。
この記事では、DISH//の『猫』を例に出して、「Aメロ」や「Bメロ」がどこを指しているのか解説していきます。
Aメロとは
Aメロは、一曲の中で最初にボーカルの歌が入る部分のことです。
インストゥルメンタル(楽器のみの曲)の場合は、最初に主となるメロディーが入る部分を指します。
コード進行やメロディーが大きく変化して、物語が展開したような感覚がするまでを一塊(ひとかたまり)として、Aメロと呼びます。
下の画像は、DISH//の『猫』という楽曲のメロディーを書いた楽譜です。
最初2小節のイントロのあと、8小節+4小節のAメロ、Bメロへ展開しています。
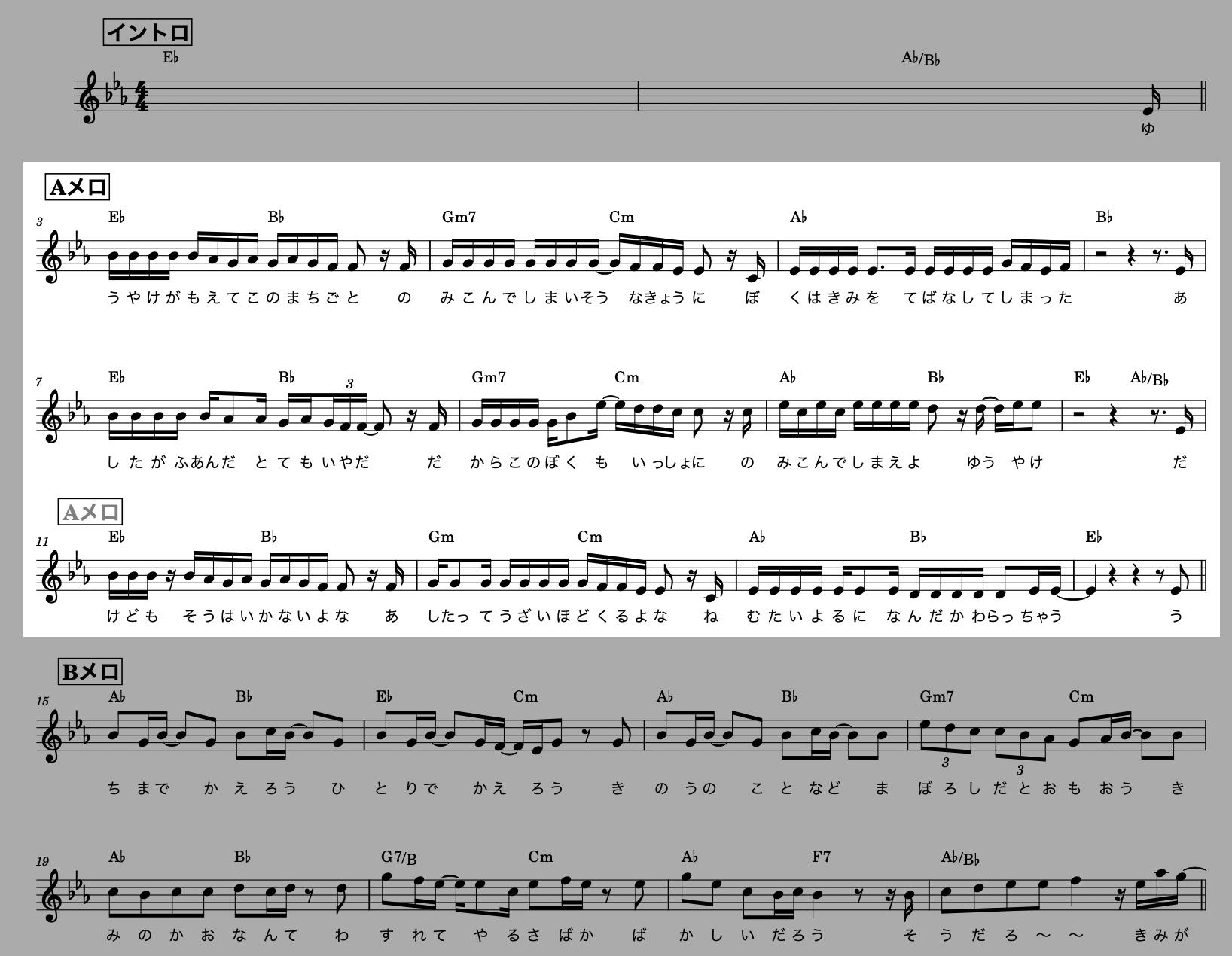
この曲の場合は、最初にAメロを8小節演奏し、ひと段落します。
その後、Aメロを半分だけ演奏します。
どちらもAメロではありますが、繰り返されたメロディーやコード進行が若干変化している場合は、最初を『A』次を『A’(えーだっしゅ)』として表す場合もあります。
曲をきいてAメロやBメロを知ろう
先ほどと同じ様に、DISH//の『猫』を参考に、各セクション(AメロやBメロなどの区別)がどこかみていきましょう。
(AメロやBメロは、ヴァースやブリッジなどの英語で呼ばれることもあるので、一緒に確認してみましょう。)
- イントロ(Intro) = 0:55 〜 1:00
- Aメロ(Verse,ヴァース) = 1:01 〜 1:37
- Bメロ(Bridge,ブリッジ) = 1:38 〜 2:03
- サビ(Chorus,コーラス) = 2:04 〜 2:31
- 2Aメロ = 2:32 〜 2:56
- 2Bメロ = 2:57 〜 3:20
- 2サビ = 2:04 〜 3:46
- 間奏(Inter,インター) = 3:47 〜 4:13
- 落ちサビ = 4:14〜 4:41
- ラスサビ = 4:42 〜 5:10
- アウトロ(Ending,エンディング) = 5:11 〜 5:24
グレーの線が引かれている『イントロ』『間奏』『アウトロ』は、ボーカルがないセクションです。
Aメロに関するよくある質問
AメロやBメロなど、なかなか感覚的に理解するのは難しかったりもします。
そこで、他の方がどの様な疑問を抱いているのか、Q&A方式で確認していきます。
Aメロに関するよくある質問
- Aメロは何小節でなきゃいけないの?
- Aメロの別名は?
- Cメロってどこのこと?
Aメロは何小節でなきゃいけないの?
特にルールはありません。
8小節のものあれば12小節、16小節の楽曲もあります。
強いて言えば、4の倍数の小節数になることが多いでしょう。
Aメロの別名は?
「Aメロ」は日本独特の言い方です。
楽譜上では、単純に「A」と表記したりします。
それぞれのセクションを表す、「A」や「B」といった記号を、リハーサルマークと言います。
また、英語圏では、日本のAメロに相当するセクションを「Verse」と言います。
Cメロってどこのこと?
「Aメロ、Bメロならなんとなくわかる」方は少なくないと思います。
日本のポピュラーミュージックのほとんどは、『Aメロ→Bメロ→サビ』を一括りで構成されています。
基本は、『Aメロ→Bメロ→サビ』だけでも楽曲は完成しますが、飽きさせないために、途中で新たなメロディセクションが加わります。
それが『Cメロ』です。